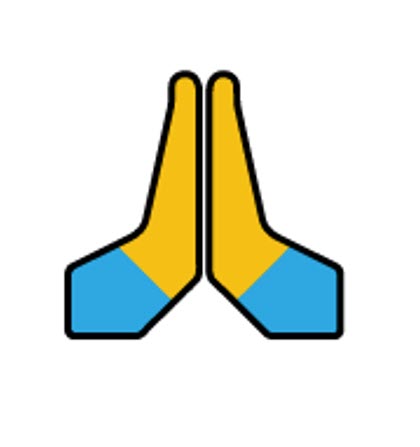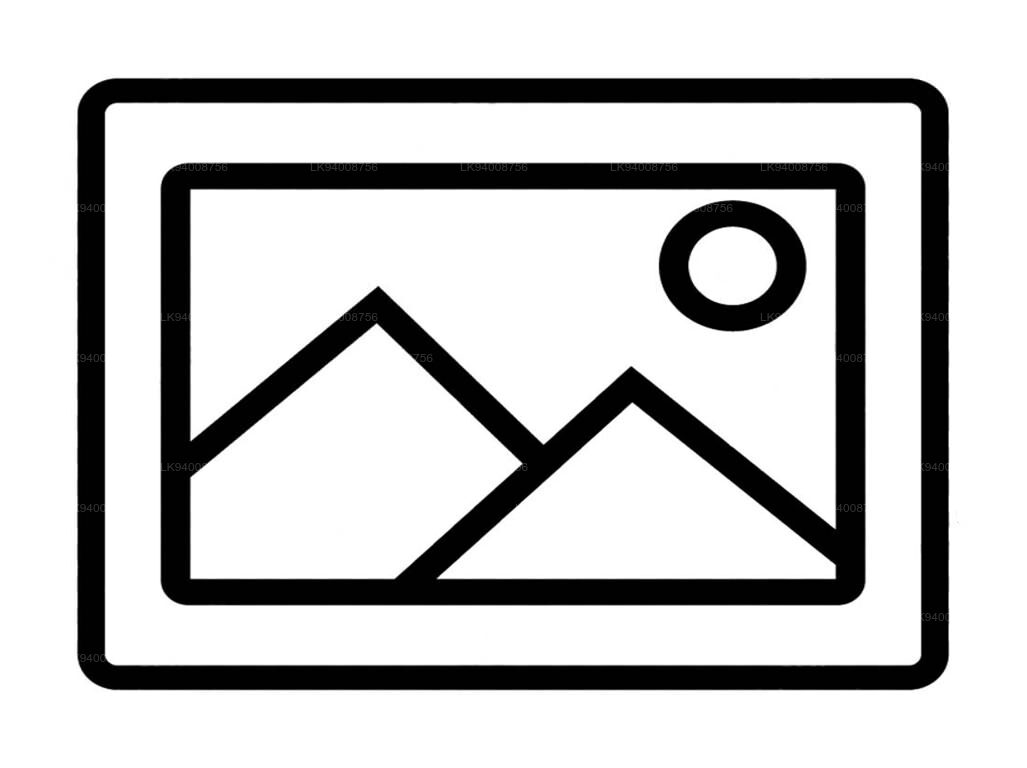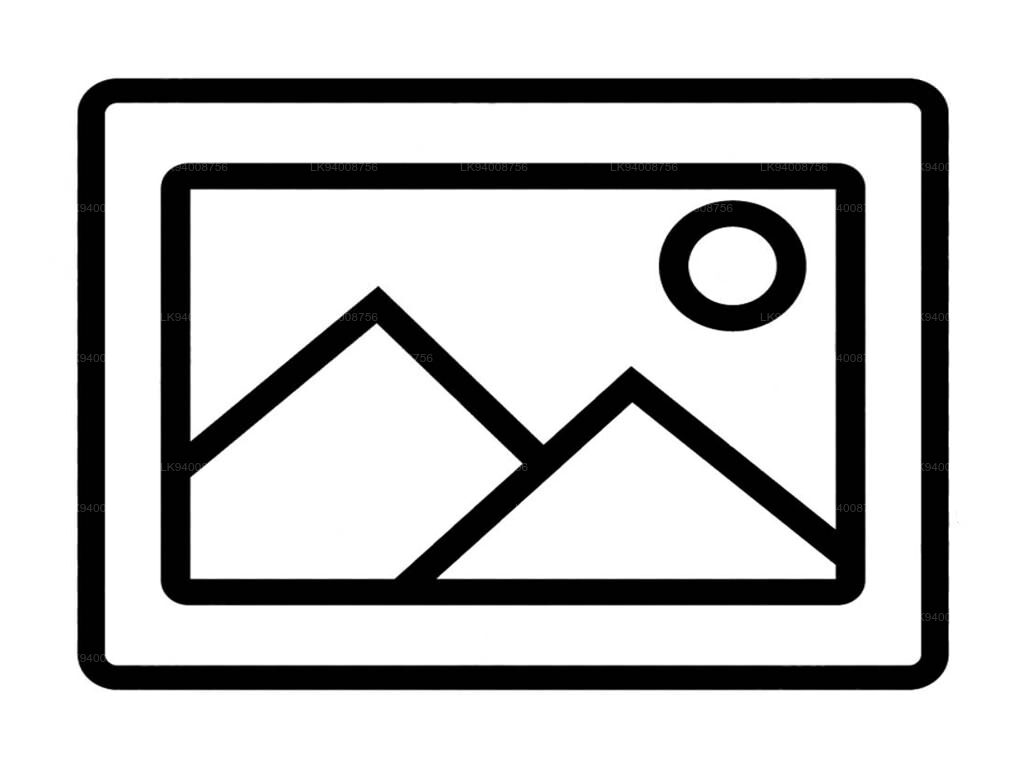涅槃 (涅槃)
涅槃(निर्वाण、サンスクリット語: nirvāṇa; パーリ語: nibbana 、nibbāna)は、仏教の道の目標です。この用語の文字通りの意味は「吹き出す」または「消す」です。涅槃は仏教における究極の精神的目標であり、サンサーラにおける再生からの救済論的解放を示します。涅槃は、四聖なる真理の「苦の停止」に関する第三の真理の一部であり、聖なる八正道の最高の最終目的地です。
仏教の伝統では、涅槃は一般に、貪欲(ラーガ)、嫌悪感(ドヴェーシャ)、無知(モハ)の「三火」または「三毒」[注 1]の消滅として解釈されてきました。これらの火が消えると、輪廻(サンサーラ)からの解放が達成されます。
涅槃は、アナッタ(無我)状態やスニヤタ(空)状態と同一であると一部の学者も主張していますが、これについては他の学者や修行僧らの間で激しく議論されています。やがて、仏教の教義の発展に伴い、心の活動の織り(ヴァナ)の欠如、欲望の排除、森からの脱出など、他の解釈が与えられるようになりました。 5 つのスカンダまたは集合体。仏教の学術的伝統では、2 つのタイプの涅槃が特定されています。それは、ソパディシェサ涅槃 (残りのある涅槃)、およびパリニルヴァーナまたはアヌパディシェサ涅槃 (残りのない涅槃、または最後の涅槃) です。仏教の開祖である釈迦は、この両方の境地に到達したと考えられています。
涅槃、または輪廻転生からの解放は、上座部仏教の伝統の最高の目標です。大乗仏教の伝統では、最高の目標は仏陀になることであり、そこでは涅槃に留まることがありません。仏陀は仏教の道を教えることで衆生をサンサーラから解放するのを助けます。仏陀や涅槃に達した人々には輪廻転生はありません。しかし、彼の教えは、涅槃に至るための導きとして、一定期間この世に残ります。
背景
涅槃の概念は、ヴェーダ文化、ヒンズー教、ジャイナ教などの古いインドの宗教にも存在します。それはシーク教やマニ教にも存在します。
語源
涅槃という用語の起源はおそらく仏教以前のもので、ジャイナ教徒、アジヴィカ教徒、仏教徒、および特定のヒンズー教の伝統の間で多かれ少なかれ中心的な概念でした。それは一般に、苦しみと再生からの自由の状態を指します。さまざまな用語を使用した精神的解放の考え方は、ヒンドゥー教の『ブリハダラニヤカ ウパニシャッド』の 4.4.6 節など、非仏教のインドの伝統の古文書に見られます。この用語は、他のスラーマン運動から意味の範囲の多くを仏教に持ち込まれた可能性があります。ただし、その語源はその意味について決定的なものではない可能性があります。
意味
苦しみからの解放と自由。モクシャ、ヴィムッティ。
涅槃は、モクシャ(サンスクリット語)、ヴィモクシャ、またはヴィムッティ(パーリ語)と同義で使用され、「苦しみからの解放、解放」を意味します。パリ正典では、2 種類のヴィムッティが認められます。
Ceto-vimutti、心の自由。それは、集中瞑想(サマーディ)の実践を通じて達成される、苦しみからの限定された自由です。ヴェッターはこれを「心の解放」と訳していますが、これは欲望を克服し、それによって欲望のない生活状態に到達することを意味します。
Pañña-vimutti、理解による自由(プラージニャ)。それは苦しみからの最終的な解放であり、再生の終わりであり、洞察瞑想(ヴィパッサナー)の実践を通じて達成されます。
Ceto-vimutti は、paña-vimutti を達成した場合にのみ永続的になります。ゴンブリッチと他の学者によれば、これらは正典の中で後から発展したものであり、初期の仏教でディヤーナの解放的な実践ではなく般若がますます強調されていることを反映していると考えられます。それはまた、古代インドにおける非仏教的瞑想実践が仏教の規範にうまく同化されたことを反映しているのかもしれない。 Anālayo によれば、「uttari-vimutti (最高の解放)」という用語は、初期仏教の文献でも輪廻転生からの解放を指す言葉として広く使用されています。
消滅と噴出
ある文字通りの解釈では、nir√vā を「吹き出す」と訳し、nir を否定語、va を「吹き出す」と解釈し、「吹き出す」または「鎮める」という意味を与えます。これは、それを消すために(何かに)息を吹きかける行為とその効果の両方を指すものと見られますが、燃え尽きて消滅する過程と結果も指します。 「吹き飛ばされ、消滅した」解放状態という救済論的な意味での涅槃という用語は、ヴェーダにも仏教以前のウパニシャッドにも登場しません。コリンズ氏によれば、「これを涅槃と呼んだのは仏教徒が最初だったようだ。
その後、涅槃という用語は、おそらく仏教の非常に早い時期に確立された広範な比喩構造の一部になりました。ゴンブリッチによれば、三つの火という数字は、バラモンが家族としてこの世での生活を象徴するために点火し続けなければならなかった三つの火を暗示しているという。この比喩の意味は後の仏教では失われ、涅槃という言葉の別の説明が求められました。情熱、憎しみ、妄想だけでなく、すべての口内炎 (asava) や汚れ (khlesa) も消滅させなければなりませんでした。その後の釈義的著作は、涅槃という言葉の全く新しい民俗語源学的定義を開発し、「吹く」を指す語根のヴァーナを使用したが、この語を「織る、縫う」、「欲望」、「」を意味する語根に再解析した。森または林":
vâna は、「風を吹く」を意味する語根 √vā に由来します。だけでなく、(匂いを)放出したり、漂ったり、拡散したりすることもあります。したがって、涅槃は「吹き出す」という意味になります。 vānaは、「欲望」を意味する語根vanaまたはvanに由来し、涅槃は「欲望なし、愛なし、願いなし」、渇望や渇き(taṇhā)のない状態を意味すると説明されています。ルート √vā を追加すると、「織る、または縫う」という意味になります。そして涅槃とは、次から次へと生を紡ぐ欲望を放棄することであると説明される。 vāna は、「森、森林」も意味する語根の vana に由来します。この語根に基づいて、vana は仏教学者によって比喩的に「煩悩の森」または 5 つの集合体を指すと説明されています。したがって、涅槃は「集合体からの脱出」または「煩悩の森から自由になる」ことを意味します。
「吹き消す」を意味する涅槃という用語は、「3 つの火」または「3 つの毒」、すなわち情熱または官能 (ラーガ)、嫌悪または憎悪 (ドヴェーシャ)、および妄想または無知の消滅とも解釈されています。 (モハまたはアヴィディヤ)。
「吹き消す」とは完全に消滅するのではなく、炎が消えることを意味します。涅槃という用語は、「彼または彼女が涅槃である」または「彼または彼女がパリニルヴァーナである」(parinibbāyati)という動詞としても使用できます。
西洋でよく使われる用法
LSカズンズは、一般的な用法では涅槃とは「仏教の修行の目標であり、平和で明晰な精神状態を妨げる不穏な精神的要素の最終的な除去と、それらが誘発する精神的眠りからの覚醒状態である」と述べた。 。
バインドを解除するには
Ṭハーニサロ・比丘は、涅槃という用語は明らかに否定的な接頭辞 nir に語根 vāṇa (束縛: 束縛を解く) を加えたものであり、それに関連する形容詞が nibbuta: 束縛されていない、および関連する動詞 nibbuti: 束縛を解くことから派生したと主張している。彼や他の人たちは涅槃を解脱という言葉を使っています。 (比丘は、この用語と「吹き出す」という初期仏教の連想は、当時の火の過程の見方、つまり燃えている火が高温の状態で燃料にくっついていると見なされていたことを考慮して生じたと主張している。そして、火が消えると燃料が放出され、自由、冷却、そして平和の状態に達するということです。
心を編むことの停止
涅槃の別の解釈は、心の活動の織り(ヴァナ)が存在しないことです。
明らかにするために
批判仏教グループの松本四郎(1950-)は、涅槃の本来の語源は nir√vā ではなく、nir√vŗ として「明らかにする」と考えるべきであると述べた。したがって、松本によれば、涅槃の本来の意味は「消滅すること」ではなく、アナトマン(アートマンではない)であるものからアートマンを「暴くこと」であったという。スワンソン氏は、一部の仏教学者は「噴出」と「消滅」の語源が仏教の中核教義、特にアナトマン(無我)とプラティティアサムトパダ(因果関係)についての教義と一致しているかどうかを疑問視していると述べた。彼らは、涅槃を消滅または解放として考えることは、「自己」が消滅または解放されることを前提としているという問題を認識しました。しかし、高崎直堂など他の仏教学者はこれに反対し、松本案は「行き過ぎで仏教と呼べるものが何も残されていない」と述べた。